森田好樹さん
プロフィール
1950年10月、三重県桑名市に生まれる。
桑名市立益世小学校、桑名市立明正中学校、三重県立四日市高等学校を経て、大阪大学医学部を卒業。
2008年6月、市立堺病院副院長在職中に逝去。
アテネの卒業生の軌跡をご紹介します。
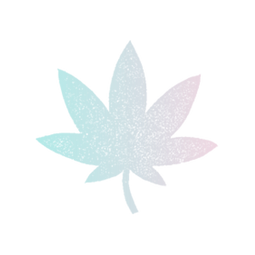
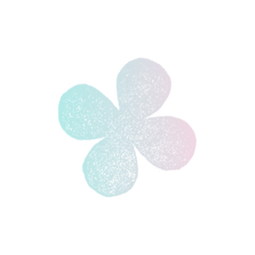
森田好樹君が亡くなったのは2008年6月、享年57歳でした。それ以降、アテネの同級生の訃報に接することが増えてまいりました。そういう今ですので、彼の足跡の一部を紹介しておきたいと思います。
好樹君は五人きょうだいの末っ子。小児麻痺の後遺症を患う次兄を家族全員で支える姿を見ながら育ちました。両親は当時最新の治療を受けさせたのですが、次兄の症状はほとんど改善されませんでした。
また、自身と長兄も喘息に長年苦しんでいました。その彼が小児科医を目指したのは当然のことだったのかもしれません。
大阪大学医学部を卒業。大手前病院での臨床研修を修了した後、市立堺病院(現・堺市立総合医療センター)に奉職。小児科を担当しました。
1996年7月、堺市の児童7892人に腸管出血性大腸菌O157による集団下痢症が発生した時には何日間にもわたって院内に泊まり込んで診療に当たりました。
病室に入りきれない患者が長椅子や廊下にあふれる、過酷な医療現場に彼はいました。不眠不休に近い状態で児童の救命に専念する彼の健康を案ずる妻に「人間、倒れてもやらなくてはならないことがある」と応えました。
彼の仕事は医療だけに留まりませんでした。国立病院の院内学級の閉鎖が決まり病院内で暮らす子供たちから教育の機会が奪われそうになった時、市立堺病院に院内学級の開設を実現させました。
その後も児童虐待防止に関する専門委員を務めるなど、亡くなるまで堺市の教育行政に協力し続けました。
地域に対する長年の貢献に御礼を申し上げたいと、告別式の日の早朝、教育委員会の方がお別れにやって来られたのでした。
病室から通学する児童を見送るために早めに彼は出勤しました。
先生に「いってらっしゃい」と声かけしてもらうことで、愚図らずに笑顔で出かけられるからだそうです。入院児童の身体の健康だけでなく心の成長と情緒の安定にも気づかっていました。
勤務医を退いた後の選択肢として、無医村に妻と共に住み、診療所の医師として働くことも考えていました。
医学部のサークル活動として、看護学生とともに何度も四国の無医村に足を運んでいたのです。
臨床研修修了後すぐに僻地医療に従事することを望んだ彼でしたが、父親の猛反対に遭い地域医療の道に進むことにしました。サークルの仲間たちも複数が彼と同じ地域医療を選んだと聞いています。
骨に転移した癌の痛みに耐えながら、海外研修に出た長女の帰りを彼は待ちました。
病状悪化の知らせを受け取った長男も続いて初任者研修先から枕元に駆けつけました。その彼の頭を撫でながら言葉をかけた後、やっと緩和ケアの処置を願い出ました。
痛みとともに意識が薄らぐ前に、妻に伝えた最期の言葉は「ごめんな」でした。
葬儀には患者さんとその父兄を始め、驚くほど多くの病院関係者が参列されました。
その中には、親御さんが押す車椅子に乗って酸素吸入をしながらやって来た子供の姿もありました。
院内学級で学んでいる子かもしれません。一時外出の許可を得て病院から来られたのだと思いました。
通夜と告別式の二日間で、医師として彼が多くの人たちに心底から尊敬され慕われていたことを知りました。
「父は患者さんの苦しみを自身のものとして生きた」。この言葉、自ら癌と戦いながらも患者さんの気持ちと痛みに寄り添い続けた晩年の姿勢だと告別式の時には思っておりました。
しかし、健康だった頃も含め彼が残した足跡のいずれからも、この姿は浮かび上がってきます。
「我が子たちをハンセン病の患者さんに会わせてあげたい」と彼は妻に語りました。
彼が医師として終生大切にしていた弱者に寄り添う心を家族はよく理解していました。
その尊敬の気持ちを遺族代表の挨拶に込めるとともに旅立つ父への別れの言葉に表したのでした。
私たちの恩師、西塚茂雄先生は堺市でのO157事件を知ることもなく1992年7月に逝去されました。
もし、ご存命だったら、医師として立派に成長した教え子の活躍を後輩たちに、まず「あの子はすごかったねえ」と前置きして、誇らしく授業の中で紹介されたと思います。
僕たちは西塚先生のそんな脱線話をいつも楽しみにしていました。
お二人の姿を偲びつつ、合掌したいと思います。
2019年10月30日
森田哲夫
1950年10月、三重県桑名市に生まれる。
桑名市立益世小学校、桑名市立明正中学校、三重県立四日市高等学校を経て、大阪大学医学部を卒業。
2008年6月、市立堺病院副院長在職中に逝去。
1950年11月、三重県桑名市に生まれる。
桑名市立精義小学校、桑名市立光風中学校、三重県立四日市高等学校を経て、京都大学農学部を卒業。
農学博士。宮崎大学名誉教授。森田好樹氏の従弟にあたる。
両名ともに小学校6年生より高校2年生までアテネ学習会で学んだ。
追記
本稿は幸子夫人および従兄姉たちからの聞き取りに私の見聞を加えて構成した。文責はすべて筆者にある。
医師だったので当然なことですが、自身が抱えている膵臓癌の厄介さを好樹君は熟知していました。しかし、意気消沈する姿を決して家族に見せることなく闘病生活を過ごしました。彼の苦衷を案じ宗教の門をたたくことを勧めた幸子夫人を「ぼくには哲学があるから」と安心させました。
中学校3年生の時でした。同じ中学校に通うアテネの仲間と出かけた隣町のキャンプ場で彼は、就寝中に入って来たマムシに手の指を咬まれる事故にあいます。入院した桑名市内の病院にはマムシ咬傷の処置の経験がありませんでした。さらに、市内に抗毒素血清は常備されておらず、事故が起きた隣町から取り寄せたもたつきが災いしました。最悪の事態は免れましたが、彼の指の機能は完全には回復しませんでした。将来、医者になって僕が直してあげると常々伝えていた次兄との約束は果たせなくなりました。精確を求められる脳神経外科の手術には繊細に動く指が必要だったのです。当初は小児科志望でなかったというこの事実を最近になって彼の姉から知りました。
病室で彼は、和辻哲郎著「日本倫理思想史」を読んでいました。見舞いに行った私は、いかめしい題名を見て気後れしてしまいました。中学生にして倫理思想かと。その後も、大谷大学で哲学の教鞭を執られていた母方の従兄箕浦恵了先輩から思想に関するお話を伺うのが楽しいと、私に語りました。幸子夫人に語った彼自身の哲学の原点はこのあたりにあったようです。そして、彼の言動に現れた医師としての倫理観の原点も。
鑑真和上と日本人留学僧栄叡と普照のことを描いた小説「天平の甍(いらか)」をアテネで読んだのは何年生だったでしょうか。同級生に尋ねても五十年以上も前のことなので誰一人確答できません。当時、テキストの題名を「てんぷらいらんか」と皆で呼んでいました。この軽薄さを根拠に中学2年生だったことにします。読了後には番外編がありました。鑑真和上が創建された唐招提寺を訪ねる小旅行です。引率は当時大学生だった塚本順夫先輩でした。近くにある薬師寺も拝観しました。盲目になった鑑真和上の像と向きあって芭蕉は「若葉して御目の雫ぬぐはばや」と詠みました。薬師寺の東塔には裳階(もこし)と水煙があります。一見、六重の塔にみえるのですが、ちいさなひさしはもこしで、本当は三重の塔だそうです。そして、水煙の解説には会津八一の和歌が引かれた気がします。旅行前の講義で得たこれらの知識は濃淡あるものの今でも記憶に残っています。西の京駅から線路を渡って大池の畔に立つ。池ごしに眺めると薬師寺の遠景がひときわ美しい。そのことも現地で教えてもらいました。この旅行をきっかけに、ある者は鑑真和上像ご開帳の日に唐招提寺を訪ね、ある者は名著「古寺巡礼」に親しみました。そして、好樹君は同じ著者の「日本倫理思想史」へと読み進んだのではないかと推測しています。
これ以前から好樹君や従兄姉たちと一緒にお寺巡りをしていたことは古いアルバムの写真からわかります。しかし、事前講義と現地指導の両方で、唐招提寺と薬師寺の歩き方を手ほどきしてもらって以降、私の古寺への関心は一段と高まりました。観月会に訪ねた唐招提寺では、明かりを灯された金堂に浮かび上がる御本尊の美しさに息を呑みました。満月を背に水煙が浮かび上がる東塔を求めて、薬師寺の伽藍を歩きました。大学時代に二度訪ねたのですが、その姿を見ることはかないませんでした。
好樹君も、家族とともによくお寺を訪ねていたようです。彼なき後も、帰省した子供達が母をお寺巡りに誘うと聞いています。我が家でも、最近、蟹満寺、唐招提寺、秋篠寺を一日で巡りました。子供達の要望だったのです。
中学2年生の時に芽生えた関心が二つの家族で次世代に確実に引き継がれていることを知り、なんだか少し嬉しくなりました。
日本全体がまだ十分に豊かではなかった1964年。受験勉強に直結するとは考えにくいこの行事に気前よく参加させてくれた親たちの大半はもうこの世にはいません。
2020年5月15日
森田哲夫
1950年10月、三重県桑名市に生まれる。
桑名市立益世小学校、桑名市立明正中学校、三重県立四日市高等学校を経て、大阪大学医学部を卒業。
2008年6月、市立堺病院副院長在職中に逝去。
1950年11月、三重県桑名市に生まれる。
桑名市立精義小学校、桑名市立光風中学校、三重県立四日市高等学校を経て、京都大学農学部を卒業。
農学博士。宮崎大学名誉教授。森田好樹氏の従弟にあたる。
両名ともに小学校6年生より高校2年生までアテネ学習会で学んだ。
追記
本稿は幸子夫人および従兄姉たちからの聞き取りに私の見聞を加えて構成した。文責はすべて筆者にある。