小学生
少人数授業カリキュラム
読書(国語)
本に親しんで語彙力と読解力をつけること、自分の考えを書くことを全学年通じて学びます。
高学年では、文章の成り立ちと文法、熟語、故事ことわざなども学びます。
小2~小4までは、児童文学と読み聞かせを専門とする先生、
小5・小6は文法や漢字・ことわざや日本の文化に精通した先生が担当しています。
教材の本は年間で2冊程度。掲載内容は過去の実績なので、変更になることがあります。
塾に通っている生徒さんの親御さんからは、「アテネに通ってから文章がうまいねとほめられるようになりました。」
「国語力が伸びたけど何か習い事は通っているのですか?と学校の先生に聞かれました」というお言葉をいただいています。
-
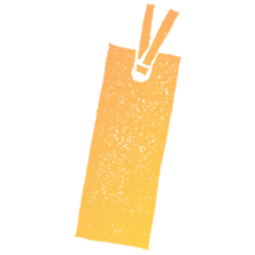
2年生
『ふたりはきょうも』(アーノルド・ローベル)
『あたまをつかった小さなおばあさん』(ホープ・ニューウェル)
他、毎回数冊の絵本の読み聞かせ、感想文、作文、遊びを交えたことばの問題 -
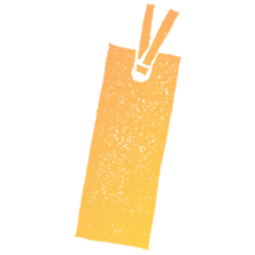
3年生
『クジラがクジラになったわけ』(テッド・ヒューズ)
『火ようびのごちそうはひきがえる』(ラッセル・E・エリクソン)
他、毎回数冊の絵本の読み聞かせ、感想文、作文、遊びを交えたことばの問題 -
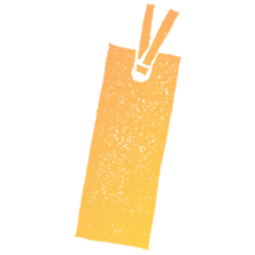
4年生
『くまのプーさん』(A・A・ミルン)
『魔術師のおい』ナルニア国ものがたり(C・S・ルイス)
他、毎回数冊の絵本の読み聞かせ、感想文、作文、遊びを交えたことばの問題 -
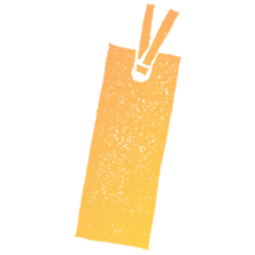
5年生
『チョコレート工場の秘密』(ロアルド・ダール)
『二分間の冒険』(岡田 淳)
他、感想文、いろはカルタ(ことわざ)、回文、漢字(同義語、対義語、部首)、文章題 -
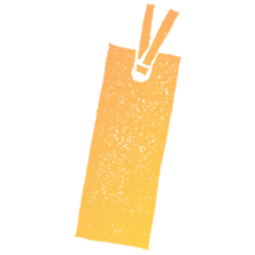
6年生
『影との闘い』ゲド戦記(アーシュラ・K.ル=グウィン)
『最後のひと葉』(オー・ヘンリー)
他、感想文、俳句かるた(季節を知る)、漢字(四字熟語、故事成語、同音異義語)、百人一首(和歌のリズムを味わう)、文章題
数学(算数)
学校の授業では、高校になると、ぐっと計算が複雑になります。
計算力が無い子は、急に計算が複雑になり、今までのギャプに置いて行かれがちです。
そのため、アテネでは高校になっても、複雑な計算でも楽にできる計算力を小学生のうちからつけることをひとつの目標としています。
また、学校では簡単に学ぶだけですが、物理や化学でよく使う「比」や約分・通分・最小公倍数・最大公約数の基礎となる「素因数分解」など、中学・高校を考えた時に大切になる項目を教えるカリキュラムを組んでいます。
通っている生徒さんからは、学校で学べないことが学べるので楽しい!という感想をいただいています。
-
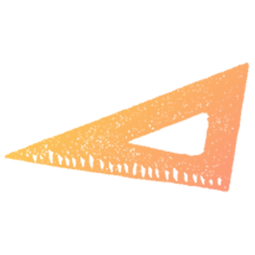
3年生【閉講中】
文章題への理解を深める
整数の加減乗除 -
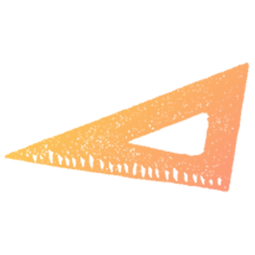
4年生
タングラム(図形への感覚を養う)
ルービックキューブ
(立体の感覚を養う)
2進数~13進数
小数の加減乗除(大きい桁のものも)
文章題(世界の文章題など) -
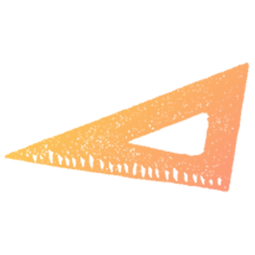
5年生
素因数分解500まで
(分数計算と約分の原理を知る)
分数の加減乗除
面積
文章題(日本の文章題:鶴亀算、植木算、時計算、旅人算など) -
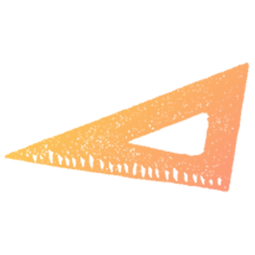
6年生
アテネ数学憲法
(式変形の原理を理解する)
体積
比
文章題
正の数と負の数の加減乗除
